支援のあり方を問う!part2
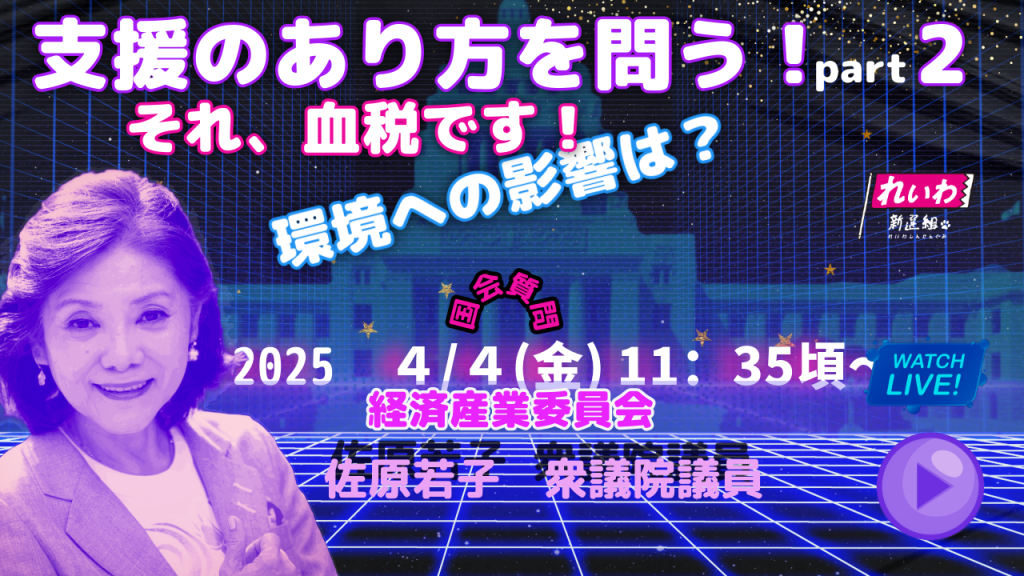

○宮﨑委員長次に、佐原若子君。
○佐原委員れいわ新選組、佐原若子です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。何度も同じようなことを聞いていて、もう飽きられているかなとも思いつつ、よろしくお願いいたします。今月、四月二日、野原局長の御答弁で、成功してリターンが上がった場合、その用途はどうするかについて、それが近くなったらまた考えますがとおっしゃっていました。投資する以上、成功させて、どのくらい利益を上げて、さらに、それをどう使って次のステップをどうするかは、投資するときに考える当たり前のことではないですか。利益をたくさん上げて、そもそもの出資者である国民にたくさん還元する、そのくらい貪欲に考えないと、また失敗するのではないですか。どうお考えになりますか。また、国策企業なので、どんどん積極財政出動で、国債発行でやっていったらどうかなとも思うんですけれども、お答えいただけますか。
○野原政府参考人事業が成功した場合のリターンにつきましては、民間出資を可能な限り促進する観点と、政府出資の回収を図る観点と、双方の観点から適切な設計とする必要がございます。今後、こうした観点を考慮しながら、産構審の次世代半導体等小委員会の意見等も踏まえまして、具体的な株式設計を検討してまいりたいと考えております。
○佐原委員ありがとうございました。半導体工場立地での環境問題に関して、ラピダスは、北海道との協定で、毎月PFAS、PFOSを測定し北海道に報告する、排水によって周辺に悪影響が出た場合は、必要な措置を取り、道に報告するとしています。測定が月ごとというのはずさんではないでしょうか。工場は毎日稼働します。国際がん研究機関で、PFASは発がんの可能性も指摘しています。悪影響を及ぼしてからの措置では取り返しがつきません。常時、毎日測定し、その値を公表すべきだと思いますが、いかがですか。
○奥家政府参考人お答え申し上げます。まず、工場排水につきましては、法令上は、PFOS、PFOAなどのPFASを測定する義務は存在していません。一方で、御指摘をいただきましたラピダスは、北海道庁との間で締結した水利用に関する協定に基づきまして、PFOA、PFOSなどについて自主測定するとともに、ラピダスと北海道庁が協議の上、地元関係者の声なども踏まえて、北海道庁に対して毎月一回報告することになったと承知しています。経済産業省といたしましても、本協定が遵守されるとともに、住民の方々の安全と安心が確保されるよう、引き続き注視してまいりたいと考えています。
○佐原委員ありがとうございました。しかし、できれば毎日報告していただきたいなと思います。これは、本当に健康に関わることです。次に質問させていただくのは、PFAS、PFOSに関する文献の差し替えのことなのですが、これは経産省の皆様の名誉に関わることなので、ここでおわび申し上げておきます。これは、経産省ではなくて、食品安全委員会でのことでございまして、こちらの経産の職員の方々のせいではないということを先に申し上げておきます。そのような、御不快になることは重々承知しておりますけれども。北海道との協定で示されているのは、一リットル当たり五十ナノグラムを基準に報告するとしています。日本の暫定的な目標値ですが、既に各報道にもあるように、内閣府の食品安全委員会での評価に際しての問題が指摘されています。三月七日に、れいわ新選組の上村議員も内閣委員会で指摘をしています。後の報道では、評価に際し、二百五十七件の参照文献のうち、評価で重要とされていたダブルA文献百二十二件を差し替えていたとあります。差し替えによって、参照にふさわしくないとされていた文献を復活させ、評価の根拠としていたとする上村議員の指摘に対し、内閣府の中政府参考人から評価手順の説明がありましたが、極めて事務的な方法を取っておられます。健康被害の可能性を示す情報が既にあるのなら、その因果関係を徹底的に追及するのが政府の責任ではありませんか。非常に緩く危険な評価だと思います。その基準値を基に協定を結び、安全の証明とすべきではありません。曖昧な評価が明らかになっている状況で、ラピダスの環境措置も厳格に法で定めるべきではありませんか。そして、現在の日本の目標値は、PFOA、PFOSの合計で一リットル当たり五十ナノグラムとなっていますが、毒性や分解のされ方が異なる物質を合算するのはおかしくないでしょうか。法的な拘束力もありません。過小評価になりませんか。アメリカでは法律で規制があり、PFOA、PFOS、個別に基準値を法で定め、それぞれ四ナノグラムです。基準も桁違いです。国が支援をするにもかかわらず、健康に関わる問題に法的な拘束力がないのは、この法案の大きな欠陥ではないですか。支援する側の責任だと思います。どう思いますか。予防原則でやっていただきたいと思います。また、経産の方々には本当に、職員の方々には失礼をしたと思っております。お腹立ちのこともあったと思います。どうぞお許しいただきますよう。
○奥家政府参考人お答え申し上げます。まず、排出規制をするべきではないかということでございますけれども、PFASを含めまして、国の法令や地方自治体の条例で定められた環境規制に、ラピダスは当然遵守していく必要はあります。ラピダスの方では、PFASのうち、いわゆる化審法で使用が禁止されているPFOS、PFOA、PFHxSと呼ばれる物質については使用しないというふうに聞いています。このような形で、きちっとした取組をラピダスはしていること、これを経済産業省としてはしっかり指導してまいりたいというふうに考えております。また、こういった取組につきましては、国際的にはストックホルム条約の方でそういったルールを定めていて、これをしっかりまず守っていくということなんだというふうに考えます。各国の取組につきましては、排水については余り、規制というか、一応ガイドラインのようなものを設定しているアメリカのような例はあるんですけれども、まだ規制については検討中ということで、いろいろな学術的な研究などもこのエリアは進んでいるというふうに認識しておりますけれども、必要な対応を適切な機関の方で検討していただいて、規制になった場合にはそれはしっかりと従っていくということかというふうに考えております。
○佐原委員それは分かりますが、やはり日本は、かつて公害というものを経験してきまして、心の中に、やはり自分は安全なところで暮らしたいと思う気持ちがあると思うので、アメリカに準じて毎日測定するとか、そのような体制にしていただきたいと思います。そして、先日、経産省の方が、御不満があったと思うんですね、私たちがやったところではないと。それはよく分かります。しかし、国策である大事なプロジェクトに向かうのであれば、省庁の垣根を越えて、本当にみんなが一緒になって、やるべきことをやって脇を締めていかないと実現できないのではないかなと思うのです。ですから、どうぞ、先ほどの問題も、予防原則ということをお考えいただいてやっていただけたらなと思います。次の質問に移ります。半導体の市場についてお尋ねします。半導体はデュアルユースですが、輸出において規制はありますか。規制があるのなら、どのような審査ルールになっていますか。教えてください。
○猪狩政府参考人お答えいたします。半導体は、その仕様、性能によりまして、外為法の規制の対象に該当する場合がございます。そのような製品を輸出する際は許可の取得が必要となっております。また、仕様、性能上は規制対象に該当しない場合でありましても、輸出時点で、大量破壊兵器などの開発、製造に用いられるおそれがある、こういうことを輸出者の方で認識されている場合には、いわゆるキャッチオール規制というものによりまして許可を取得する必要がございます。我が国としましては、軍事転用を未然に防ぎまして、国際社会の平和及び安全の維持を期する観点から、引き続き厳格に輸出管理を実施してまいりたいと考えております。また、輸出者に自主的な輸出管理の取組を促すとともに、税関等の関係省庁と協力して、外為法の運用や執行の実効性向上に取り組んでまいりたいと思います。
○佐原委員ありがとうございました。輸出許可は、世界のどこの国に対しても同条件で審査するのですか。
○猪狩政府参考人お答えいたします。外為法におきましては、全ての国に対しまして、国際社会の平和及び安全の維持の観点から、軍事転用懸念があるかどうかという観点で輸出管理を行ってございます。特定の国をターゲットにするということではなく、全ての国に対して輸出管理を行っております。
○佐原委員日米半導体協力基本原則では、両国は、半導体サプライチェーンの強靱化のために同志国、地域と協力して取り組むこととしています。同志国とはどの国を指しますか。あるいは、この法案に関わる政策での同志国はどこですか。同志国以外にも輸出できるのですか。教えてください。
○武藤国務大臣日米半導体協力原則ですけれども、これは、半導体サプライチェーンの強化に向けて、市場経済また自由貿易を前提に、日米及び同志国、地域が相互補完的に取組を進めるもので、特定の国に対して半導体の輸出を規制するものではありません。その上で、半導体のサプライチェーンですけれども、半導体の製造、設計に加え、製造装置や部素材、原料も含め、幅広い産業、技術領域から構成されているものであります。一国だけでサプライチェーン全体を賄うことは、これは困難であります。同志国との連携が不可欠であって、また一方で、国際秩序が非常に不安定化する中で、米国のみならず、EUですとか英国、オランダ、インドなど、多様な国との半導体協力に関するパートナーシップを締結することで、我が国として強固な国際協力の枠組みを構築してきているところであります。引き続き、同志国等と連携しながら、我が国半導体産業の復活に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
○佐原委員同志国以外でも輸出は可能だということですか。
○猪狩政府参考人お答えいたします。外為法の対象になっている半導体につきましては、同志国、同志国以外かかわらず、軍事転用の有無などを確認しながら審査を行ってございます。ですので、軍事転用の懸念がない、そのような場合には同志国以外にも輸出許可は可能だと考えております。
○佐原委員これまで、参考人の皆様のお話や委員の皆様の議論、また省庁の皆様から伺ったラピダス支援までの経緯から、日本の半導体産業がアメリカの対中国政策、経済安全保障の構図に組み込まれている感が否めません。アメリカから中国に輸出規制をかけるように要請されたら、従いますか。
○猪狩政府参考人お答えいたします。外為法におきましては、例えば外国において軍事に転用される、そういう懸念があるかどうか、そういう観点から輸出管理をあくまで行っております。あくまで、安全保障の観点から、我が国の判断として輸出管理を行っているところでございます。
○佐原委員ありがとうございました。かつては、TRONという、皆様御存じだと思いますけれども、TRONというOSをつくった天才、坂村教授、月尾教授というお二方がいらっしゃいましたが、今なおTRONは世界的にいろいろ使われております。しかし、このとき、スーパー三〇一条でアメリカにはしごを外されてしまい、圧力をかけられてしまいましたね。そういったことで、また日本はそういったアメリカの圧力をはね返すことができるでしょうか。
○奥家政府参考人お答え申し上げます。半導体の日米の関係につきましては、非常に密に信頼関係を着実に構築してきています。まず、バイデン前政権との間では、両国の半導体サプライチェーンを補完的に強化していこうということで、先ほどもお話がありました日米半導体協力基本原則などを結びまして、次世代半導体の開発に関する共同タスクフォースを設置するなどの取組をしています。現在のトランプ政権におきましても、先ほども質疑でありましたが、二月七日の日米首脳共同声明で、先端半導体などの重要技術開発で世界を牽引するための協力を両国が追求するということを明記しています。その後も、閣僚レベル、事務方含め、各レベルでアメリカ政府と直接対話を行っています今後も、様々な機会を捉えまして、御懸念の点を解消できるよう、トランプ政権との間で半導体に関する協力を深めていきたいというふうに考えています。
○佐原委員ありがとうございます。NTTの光半導体のテクニック、技術力、そういったものは、日本の中でやはり守っていかなければならないと思うんですね。ですから、その点をお願いいたします。ありがとうございました。また、使用電力について、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。ラピダスは、使用電力について、自然エネルギーの使用を前提にしています。さくらインターネットの田中社長も、そのようにおっしゃっていました。これに関して、原子力は使わないということを明確にしていただきたいと思っています。国民の安全が第一です。ラピダスへの巨額の支援は、国民の血税です。血税で作るものに原発を使うことは、私は許せないんですね。原発は、多くの命を奪いました。生活や人生を奪いました。ここで、是非お願いしたいのです。泊原発は絶対再稼働しないと約束していただきたいんです。ラピダスの工場のために原発を使うということは、道民への裏切りだと思います。道民の健康と安全を守ってください。皆様の血税が投入されているんです。だからこそ、原発ではなく再生可能エネルギーを使ってほしいと思うんです。今、日本は地震活動期です。原発の安全神話は、今はもうありません。原発は、スイッチ、オン、オフがすぐできるわけではありません。また、冷却水は、七度温度を上げて海に放出されています。そういったことで、是非とも、環境保全の意味からも、地球温暖化の意味からも、原発からできるだけ再生エネルギーをというか、完全に再生エネルギーを使っていただきたい、そうお願いをいたしまして、大臣のお答えをいただきたいと思います。
○武藤国務大臣委員の御懸念は、いつもこの委員会でもお聞きしておりますところであります。ただ、私どもも、やはり、電力の安定供給を考えなきゃいけない、国民の生活を守っていかなきゃいけない。一方で、特にラピダスの、また話が出てまいりました。いずれにしましても、原子力発電所の再稼働については、これは、原子力規制委員会が、新規制基準に適合するかどうか、これを認めた場合のみ、地元の御理解があった上で、これは動いてくる話でありまして、この御懸念、これは真摯に受け止めながら、まだまだ解決しなきゃいけない課題もございますので、真摯にこれからも進めていきたいというふうに思っております。
○佐原委員様々な懸念があるということを理解していただいたということで、是非とも、原発ではなく再生エネルギーということで行っていただきたいな。国策企業ラピダス、前途のために、こういった事故がないようにしていただきたい。是非とも新しい考えに従ってほしい。何か希望が見えてくる、そういうものにしていただきたい。国民の血税を使っているのだから、原発に回帰することは、私は反対です。これが新しい日本の幕開け、そして、世界に対しての新しい日本の力を見せるところではないかなと思っています。そう願って、原発を使用しないことを願って、質問を終わらせていただきます。長々と、ありがとうございました。失礼いたします。
YouTubeはこちら↓
