支援のあり方を問う!part1
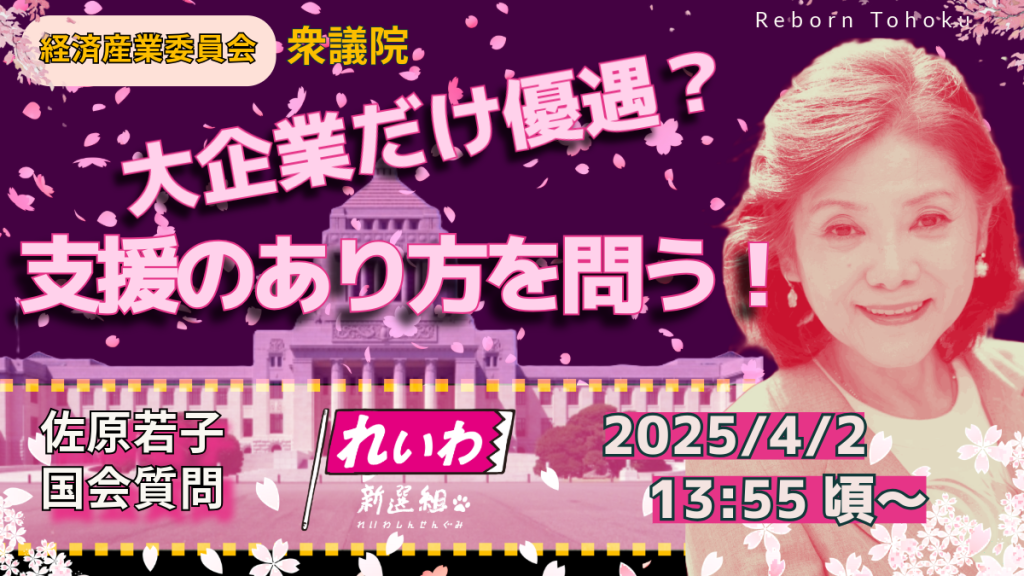

○宮﨑委員長次に、佐原若子君。
○佐原委員 れいわ新選組、佐原若子です。今日は、御質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。しょっぱなから申し訳ありません。通告していないのですが、まず大臣にお尋ねいたします。今回の半導体生産企業への支援のお金はどこから出ていますか。端的にお答えください。
○野原政府参考人 今回の当初予算の分、一千億円でございますが、これは一般会計からでございます。フレーム自体は三種類の財源の組合せになっていまして、財投特会の投資勘定からの繰入れ、それからGX債の活用、それから経産省の関係での基金からの国庫返納金、この三つが主要なものでございます。ちょっとそれ以外のものがちょろちょろっと入りますけれども、基本的にはその三つです。
○佐原委員ありがとうございました。国民の血税ですよね。国が支援したお金で、そこから生まれた利益をどう還元するか、まず明確にしてほしいと思っています。例えば、これからいろいろな方が投資して、量産に成功して利益が上がっていく、そして、出資者にその利益が還元されるというのは、ちょっと納得いかないと思うんですよ、国民としては。国が支援してきた分はしっかりと株式を保有して、その配当は例えば基金をつくって環境や福利厚生に生かすとか、そういうお考えはないでしょうか、大臣。今こそ公益資本主義の先鞭を経済産業省に切ってほしいと思うんですけれども。
○野原政府参考人 投資した後のリターンが、成功して株価が上がった場合のリターンが出て、投資した額よりもたくさんもうかった場合どうしますかというお尋ねかと思いますが、これは、それが近づいてくれば、どういうふうにそれを活用するかという話になると思いますけれども、法律上の、会計上の取扱いは法律に細かく規定がございますので、それを御参照いただければと思います。
○佐原委員できれば国民に還元していただきたいなと思っております。半導体産業の考え方についてお伺いします。一九九〇年代、日米半導体協定によって衰退した日本の半導体産業をいま一度復活させるための支援だと思いますが、過去三十年間、日本に残された技術を育てるために、基盤の技術研究など、継続的支援を行うべきではなかったのでしょうか。それとも、支援があっても目に見える成果がなかったのでしょうか。お伺いしたいと思います。また、日米半導体摩擦のように、またアメリカから横やりが入らないですか。入ったらどうされますか。お伺いします。
○武藤国務大臣今日もずっとこういう議論を重ねてきております。過去の検証も含めて、その上でこのラピダスについて今向かってきているところであります。今、これまで何もしなかったのかというようなちょっと御発言もありましたけれども、現実は、場合によって必ずしも実証できなかった事実はあるんですが、それなりにずっと残ってきている会社もそれぞれございまして、半導体は、今回、次世代ということで、新しい試みに今展開を図ってきているところであります。今、今日もありましたけれども、成果が上がらなかった理由は、多数の国内企業が参加する中でリードする企業がはっきりしなかったとか、研究開発面が強調されて、民間企業の巻き込みが十分でなかったこととか、最先端の技術を有するグローバルな事業者との連携が不足してきた等が挙げられると今日も申し上げてきました。いずれにしましても、こういうことだろうと思うんです。簡単に申し上げますと、なかなか、まずお客さんというのが見つけてこなかった。研究開発という形の中でも、個社の中での判断というのが非常に強かった世の中でした。今回、次世代ということになりますと、これは相当お金がかかるということもあって、国も投資をしながら、そういう形で新しい枠組みをつくる。そして、各国とは、アメリカのIBMですとか、またベルギーのimecといった、先端的なそういうところとも連携をしながら、今回は新しくやってきているところであります。実際のところ、顧客開拓につながる設計の開発支援、これも非常に大事なこれまでの反省の検証の結果です。そういう形の中で政策を進めて、しっかりとした形で具現化をしていきたいというふうに思っています。
○佐原委員ありがとうございました。何度も午前中と重複したような質問で申し訳ございません。経産省へのヒアリングで政府支援の成功の事例をお尋ねしましたところ、台湾のTSMCを挙げられました。資本の四八%を政府が占める、事実上の国有企業同等の形でスタートしました。対してラピダスには、これまで委託研究開発という形で、また今後も出資をするものの、民間出資を期待するものです。しかし、産業育成を図るなら、当初からしっかり資金を投じ、国策企業として育て、人材も集めるべきではなかったのでしょうか。それであれば、経営の透明化、ガバナンス、またPFASなどの環境問題にも責任を持って対処できると思いますが、いかがですか。
○武藤国務大臣公営企業にするべきではなかったかという御趣旨だというふうに思います。最先端の半導体をめぐる世界の技術動向ですとか市場動向の変化というのは、もう本当に近年ますます激化しているところで、加速化しているところであります。これに対応しながら次世代の半導体の量産事業、これを確立するためには、やはり、民間の活力を生かしながら、経営判断の迅速性とか柔軟性、これを最大限確保する必要があると認識したところであります。このため、民間企業であるラピダスに対して、国が研究開発委託する形式が望ましいという判断をされたところでありまして、また、外部有識者も交えて進捗管理等を行うことで、適切なガバナンスを実施していかなきゃいけないということになると思います。本法案に基づいて、金融支援につきましても、次世代半導体等小委員会というものがありまして、経営の過度な介入は避けることが示されており、この方向性に沿って検討を深めてまいりたいと思っているところであります。
○佐原委員ありがとうございました。れいわ新選組は、半導体生産に積極財政で補助することを供給力強化の観点から必要と考えていますが、今回のやり方は、特定企業への支援のための法案と言えます。今後の産業支援の在り方に影響を及ぼすのではないでしょうか。一社が継続して支援を受け続けることにならないでしょうか。一社への支援が余りに多いため、自助努力に影響するのではないでしょうか。企業間の競争が抑えられてしまうのではないでしょうか。いかがでしょうか。
○奥家政府参考人お答え申し上げます。初めに、先ほど、今年の当初予算、一般会計からということで御説明をさせていただきましたけれども、財政投融資特別会計の投資勘定からの繰入金を活用するということで訂正をさせてください。いただきました御質問に対するお答えであります。まず、今回、次世代半導体の支援スキーム、これにつきましては、複数年度にわたる相当な規模が想定されています。支援対象事業者を厳に限って、政策資源を集中的に投下して、次世代半導体の量産を迅速かつ確実に実現させる必要があるだろうというふうに考えています。そのためには、最も適切な事業者を公募により一者のみ選定、これをしっかり支援するというふうに考えています。その上で、選定につきまして、法案に基づく次世代半導体製造事業者への支援規模については、公募を通じて事業計画は提出されてきて、これを厳格に審査して、外部有識者の意見も踏まえまして決定していく。また、その後の進捗管理につきましても、マイルストーンを適切に設定して、その達成状況を確認しながら、支援継続の要否を含めて対応していく。自助努力を阻害する事態は生じないものというふうに考えています。また、競争環境につきましてですけれども、次世代半導体の分野につきまして、海外トップメーカー間の熾烈な国際競争が行われています。企業間の競争が抑制されるとの御指摘には当たらないかなというふうに考えております。
○佐原委員ありがとうございました。ラピダスが事実上の選定企業になるとされていますけれども、ほかにも何社か候補になった企業はあるのでしょうか。
○奥家政府参考人お答え申し上げます。本法案において、指定した半導体ごとに、公募を通じて支援対象となる事業者を選定することとなっております。政府としては、まずは、次世代のロジック半導体のみを指定することを想定しています。次世代半導体の量産を目指す事業者、国際的に見ればラピダス以外にも存在するわけですけれども、本法案に基づき申請を検討しているかは承知しておりません。
○佐原委員分かりました。今のところラピダス一社だけが候補だとしたら、選定に比較対象がなく、ゆえに審査基準が甘くはなりませんか。お伺いします。
○奥家政府参考人お答え申し上げます。本法案における公募プロセスでは、あらかじめ公募の実施に関する指針を定めて公表した上で、申請事業者の実施計画の内容が指針に照らし適切なものであるか、事業者が次世代半導体の生産を行うに足りる技術的な基礎を有するか、こういったことなどの基準に適合するかどうかをしっかり審査して、基準に達しない事業者は、当然のことですけれども、支援対象事業者として選定されない仕組みとなっています。その上で、基準に適合する事業者が複数存在する場合には、指針に定める評価基準に従って厳格に評価を行って、最も適切な事業者を一者選定する、こういう仕組みになります。また、選定に当たりましては、産業構造審議会の次世代半導体等小委員会、専門家の方々に集まっていただいて、申請事業者と利害関係がないことを確認した外部有識者の意見も踏まえて審査を行うということでございますので、公平かつ厳格な審査が担保されるものというふうに考えております。
○佐原委員分かりました。ありがとうございます。ラピダスは少量多品種生産を掲げていますが、安定した大きな需要、市場の獲得につながるのでしょうか。経営方針、経営状況のチェック、審査、場合によっては改善の協議や指導が必要と思いますが、その仕組みはありますか。先ほどもお伺いしましたよね。
○奥家政府参考人お答え申し上げます。まず、先ほども、少量多品種ということは、少量ということではないので、そういったところをちょっと誤解を持たれないようにお願いをさせていただきたいなと思っております。その上で、半導体のグローバル市場のうち、七ナノ以下の最先端領域の需要は、二〇二〇年の約七兆から二〇三〇年には五十三兆まで伸びる見込みです。特に、ラピダスが二〇二〇年代後半に量産開始を目指す二ナノ以下の半導体についても、やはり生成AIでこの普及、その利活用が拡大していくことによって、市場規模は急速に拡大していくというふうに見込んでいます。その上で、近年、最先端半導体の製造に要する期間が非常に長期化しています。半導体設計企業などの顧客側においては、短納期製造を求めるニーズが非常に強いです。ラピダスは、まさにその短納期製造に適合した生産方法を実現しようということで、複数のウェハーをまとめて処理する、いわゆるバッチというものではなくて、ウェハーを一枚ずつ流して処理する枚葉式を採択するなど、いわゆる受注から納入までの期間を短納期化することを目指しています。こういった取組は、TSMCやサムスンなどの既存の企業とは異なる競争軸というふうになります。新たな顧客価値を提供することができるというふうに考えています。こうしたラピダス独自の事業戦略につきましては既に価値を見出されていまして、先ほどちょっとお話しさせていただきましたIBMであるとか、そういったところも非常に価値を見出して、使いますというような形で既に話が動いていて、今後も顧客拡大を期待できるかなというふうに思っております。改善の方向ということで、改善が必要な場合ということですけれども、次世代半導体小委員会で、こちらは外部有識者も交えまして、事業の進捗管理については、マイルストーンをしっかり設定した上で、達成状況をしっかりモニタリングする、状況の変化に合わせまして事業計画の見直しも検討する仕組みとなっております。経営状況などをしっかり確認しながら、必要な対応をしっかり取ってまいりたいというふうに考えています。
○佐原委員そういったチェック体制は是非完全な第三者による組織をお願いしたいと思っております。また、この半導体支援で泊原発を再稼働させるというようなことはないでしょうか。データセンターとか生成AIは大量の電力が必要だということをよくおっしゃるんですけれども、原発が必要だという。しかし、光半導体などのIOWN構想などを見てみると、光を使う場合に大変その電力の消費量が実は減らすことができるというすばらしい技術だということを、調べてみたらあったんですね。じゃ、いわゆる脱原発に関してもこれは悪くないぞと私は思ったんですけれども、いかがでしょうか、泊原発の再稼働については。
○武藤国務大臣省電型の半導体ということで、大変期待をされているところでもあるのは承知しています。ラピダスは、次世代半導体、これはもう全般的に言えることですけれども、量産のためには、量、価格共に安定的な脱炭素電源の供給確保が重要であるということは、これは説明を受けているところであります。泊発電所の再稼働については、北海道の電力の安定供給と脱炭素化に大きく寄与するとともに、電力価格の抑制にもつながるものと認識はしているところであります。我が国全体として、DXあるいはGXの進展により電力の需要増加が見込まれる中で、脱炭素電源の確保が国力を左右する状況にあります。低いエネルギー自給率あるいは火力への高い依存といった課題を克服する観点でも、脱炭素電源の確保が必要になるということだろうと思います。原子力発電所の再稼働につきましては、これは、規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合のみ、地元の御理解を得ながら再稼働を進めていく方針でありまして、様々な御懸念の声があることも真摯に受け止めたいと思いますし、それぞれの課題にしっかりと取り組んで、丁寧に説明を行いながら、原子力については活用していかなくてはいけないと思っております。
○佐原委員それはもちろんそのようにいつも御説明をいただいているんですけれども、この半導体の開発をして、そしてまた、NTTのすばらしい技術があるわけですよね、光。そういったことを、やはり脱原発をすることにより、エネルギーをなるべく消費しないような方向に使っていただくと、それはそれでたくさんの税金を使っていくということに対しての納得ができるんですけれども、それでもやはり原発が必要というのであれば、その意味は何なんだろうというふうに思うんですよね。やはり、原発は死に行く、滅び行く恐竜とおっしゃった学者の先生がいらっしゃいますけれども、いいかげん、地球温暖化とかそういうことを本当に真剣に、いろいろな省庁をまたがって、みんなで、国民も一緒になって考えていかなければいけない待ったなしの状況にあるということは皆さんもう御存じだと思うんですよね。ですから、それを是非、この光半導体を使って新しいエネルギーの在り方を一緒に考えるべきじゃないかと思うんですよね。原発だのITERだの、エネルギーを大量消費をする時代は終わったんだと思うんですよ。光半導体とかそういうことを作るのに電力が必要だというのであれば必要かもしれませんが、さくら、この間の田中社長さんですよね、一〇〇%自然エネルギーでやりたいと思っているというようなお話もしていたので、是非とも、そういった意味で、半導体をたくさんの国民の税金を使ってやったりするのであれば、この問題からやはりちょっと一歩ほかの方向を目指して、脱原発の方に行っていただきたいなと思いつつ、るる重複した質問をいたしまして、お答えいただきまして、どうもありがとうございます。是非、公益資本主義というのが今ちょっとはやっております、世界で。だから、この日本がその先鞭を取って、公益的な資本主義の中ですばらしい成果を上げていただけるよう、また、そのナノサイズ、それが達成できることを願って、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
Youtubeにて配信しております。ご覧ください>>
