経済産業委員会
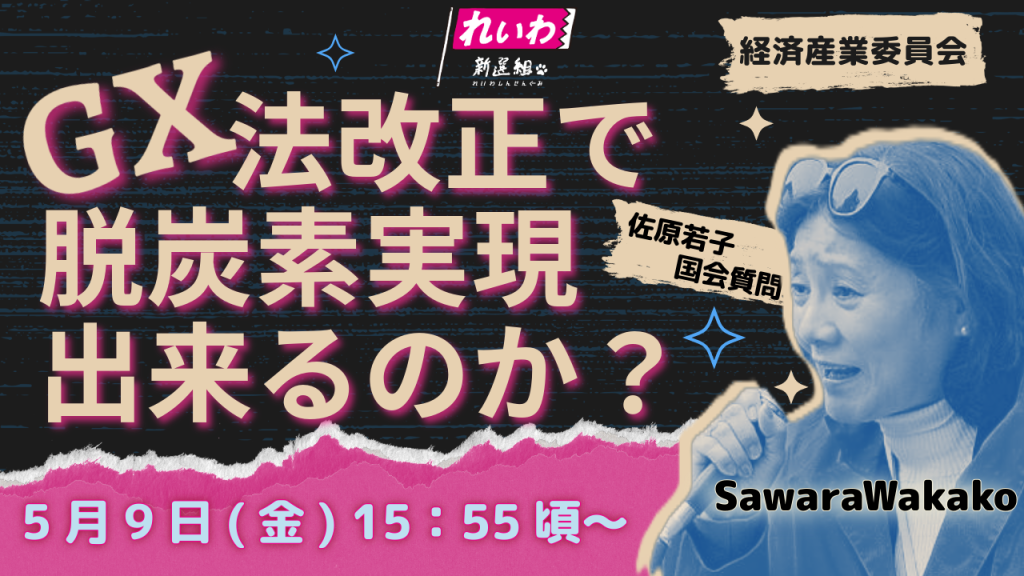

○宮﨑委員長次に、佐原若子君。
○佐原委員本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。れいわ新選組、佐原若子です。よろしくお願いいたします。日本の制度では、排出枠取引においてカーボンクレジットが利用可能となっています。EUでは、国内外共に不可とされています。カーボンクレジットの利用は、脱炭素推進への影響はどのようにお考えですか。想定される影響とその理由を御説明いただけますでしょうか。
○武藤国務大臣 カーボンクレジットについての御質問をいただきました。多様な主体による脱炭素の努力をクレジットとして取引を行うことで、社会全体で費用対効果の高い取組を進める手法であります。我が国では、政府が運営する制度として、中小企業、自治体、個人など様々な主体による排出削減量、吸収量を認証するJクレジット制度、また、我が国の脱炭素技術等の導入により実現された途上国等の排出削減、吸収への貢献を定量的に評価をする二国間クレジット制度、これはいわゆるJCMとよく言われています、が存在しているところです。例えば、Jクレジット制度では、これまで累積で既に約一千百万トンが認証されておりまして、脱炭素に寄与している実績がございます。そして、排出量取引制度においても、これらのカーボンクレジットを活用可能とすることで、カーボンクレジットへの需要が高まり、その活用を通じた排出削減が促進をされ、社会全体での脱炭素の取組が更に加速するものと考えているところであります。
○佐原委員 大臣、ありがとうございました。では次に、排出枠取引において、排出枠価格が下落したときには、GX機構、つまり政府が買い支えするとしています。この仕組みは、脱炭素の推進にどのような影響があるとお考えでしょうか。想定される影響と理由を御説明ください。
○武藤国務大臣 排出量取引制度では、事業者間で市場を通じて排出枠の取引が行われることにより、炭素の排出に値づけがされます。そして、この炭素価格の水準が安定的に上昇していく見通しを示すことで、炭素価格が投資判断の際の指標として機能をして、社会全体のGX投資が促進されるものと考えているところです。こうした観点から、炭素価格の水準の将来的な見通しを示すため、上下限価格を経済産業大臣が認定することとしているところであります。御指摘の買い支えでありますけれども、この下限価格を担保するための必要な措置であります。下限価格があることで、先行してGX投資を行い、排出量を削減した企業が、排出枠の余剰を売却した際に得られる収益の最低水準が明らかになるということだと思います。これにより、GX投資の収益の予見性が得られるため、投資が促される効果があると考えているところであります。
○佐原委員 分かりました。ありがとうございます。ただ、先ほどJクレジットの手続が煩雑だとおっしゃった議員がいらっしゃいますので、このことはよろしくお願いいたします。私もそう思います。
次に、炭素の排出は公害と同様に考えるべきものと思います。大量の炭素を排出した事業者が、防止策だけではなく、事後の問題にも責任を負うべきものです。排出枠取引、化石燃料賦課金が価格転嫁され、消費者に負担がかかる可能性は想定されていらっしゃるんでしょうか。また、このコストが価格転嫁されることについてはどのようにお考えになりますか。
○田尻政府参考人 お答え申し上げます。GX政策は、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現を目指し、中長期の産業構造転換を見据えて実施するものでございます。したがいまして、事業者の責任を問うという姿勢ではなく、GX投資を促し、実際の排出削減行動にいかにつなげていくかという視点が重要かと考えてございます。議員御指摘のように、一律に排出者から消費者への転嫁を認めない場合には、脱炭素投資が単なるコストとして認識をされまして、事業者が投資にちゅうちょする結果、社会全体の排出削減は進まないという懸念があると考えてございます。事業者がGX投資を進めるためには、投資を通じて生み出した製品、サービスに対して、消費者から適正な対価を得られることが必要かと思ってございます。つまり、対価の支払いを通じて、炭素のコストを、事業者だけではなく、消費者を含めた社会全体で分担する仕組みであることがGX投資を進めるためには必要というふうに考えているところでございます。
○佐原委員 ありがとうございました。国民も一緒に負担するということですね。排出枠取引は、二〇三三年以降、発電事業者を対象に有償化するということですが、ほかの事業者への拡大の計画はあるのでしょうか。どのような分野へどの程度広げるのか、脱炭素の目標をどこに設定しているのか、そしてその目標達成までのプランをお示しください。
○武藤国務大臣 排出削減目標のロードマップみたいなものということで御質問というふうに理解をしていますが。二〇五〇年カーボンニュートラル等の国際公約の実現に向け、GX二〇四〇ビジョン、いわゆる地球温暖化対策計画、またエネルギー基本計画、この三つに基づいて、二〇四〇年に向けた目標を設けた上で、政策を総動員して取り組むこととしてきているところであります。この中で、御指摘の排出量取引制度における有償割当てについてですけれども、二〇三三年度から発電事業者を対象に導入することとしています。有償割当ての導入に当たっては、代替技術の導入可能性等も踏まえつつ、国民生活や産業への影響を踏まえて制度設計を行うことが重要だというふうに思います。その中で、発電部門につきましては、排出量の四割を占め、脱炭素の重要性が高く、再エネなどの商用化された代替技術を有しています。また、諸外国でも先行的に有償割当てを導入しているところもございます。このため、我が国でも、発電部門をまず対象にすることが適切と判断しているところでありますけれども、現時点でそれ以上に対象業種を拡大する計画はございません。
○佐原委員 ありがとうございました。次に、アメリカとの貿易に不透明感が増す中、EUとの貿易の重要性は増していると思います。EUでは、CBAM、カーボン・ボーダー・アジャストメントの導入によって、輸入商品に対して、EU域内と同様の炭素価格が課されます。日本の排出枠取引制度は、EUとの貿易において、日本の産業にとって有利に働くとお思いでしょうか、それとも不利に働くとお思いでしょうか。
○田尻政府参考人 お答え申し上げます。今御指摘のございました、EU・CBAM制度でございますけれども、この中身でございますが、まずEUが、EUの域外から鉄やアルミニウムなど六つの分野の対象製品を輸入する際に、製造過程における炭素排出量に応じて課金をするという仕組みでございます。EUは、このCBAMの仕組みの導入を決定をしてございまして、今、移行期間を経て、二〇二六年一月から本格的に実施される予定と認識をしているところでございます。日本企業への影響ということの御質問でございましたけれども、日本からEUに対して、例えば鉄とかアルミニウムというものについては、重量が重いということもございまして、それほど多くの輸出をしているものではございませんので、現時点で、仮にこの六つの分野だけであれば、それほどの大きな影響ではないかと思って想定してございますけれども、ただ、とはいいながらも負担がかかるということは事実でございまして、一定程度の負担があるんじゃないかというふうには想定しているところでございます。
○佐原委員 一定程度ということですね。次に、日本の排出枠取引の制度が、脱炭素推進と日本の産業振興の両観点から有効に機能すると考えますか、あるいは難しいと考えますか。理由も併せてお聞かせください。
○田尻政府参考人 お答え申し上げます。累次御説明させていただきましたとおり、この排出量取引制度につきましては、カーボンプライシング制度の一環ということで、二十兆円の経済移行債を基にした日本企業へのGXの投資の支援というものをカーボンプライシングの仕組みによって後から回収をする、その原資となっているというものでございますので、この両者を合わせました成長志向型のカーボンプライシング構想というところで日本の脱炭素と経済成長を両立させていくということを目指しているものでございます。
○佐原委員 ありがとうございました。なかなか今難しい時代になって、例えば、この間、ドイツのソーラーパネルの会社、ワールド、何でしたっけ、が倒産いたしましたよね。そういうふうにやはり中国のいわゆる安売り攻勢に負けてしまうというようなこともあって、やはり、例えば先般ラピダスにはかなりの支援をするということだったんですけれども、これからは日本のそういった企業に対して支援をしていっていただきたいなとも思います。
次に、資源法において、環境負荷に対し優れた製品設計に支援をする内容があります。この支援に至った理由、経緯を御説明ください。
○武藤国務大臣 ありがとうございます。再生材の利用を促進するためには、リサイクルの高度化と併せて、解体、分別しやすい設計や製品の長寿命化につながる設計を推進していくことが不可欠であります。その一方、現行制度では、特に優れた製品設計を評価をし、市場での差別化を図る仕組みが存在していません。このため、解体のしやすさや長寿命化など、ライフサイクル全体での環境負荷低減に資する優れた製品設計を評価をし、認定する制度を創設することとしたところです。認定を受けたことを製品に表示することで、消費者が環境に配慮された製品を選択することを促す効果を期待しているところです。また、認定製品につきましては、国等による調達での配慮等を行うとともに、環境配慮設計の実現に必要な技術開発支援も実施してまいります。これにより、企業に対する環境配慮設計への投資インセンティブにつながるものと考えているところです。
○佐原委員 ありがとうございました。私も、ジャパン・メイドの製品を、どんどんどんどん皆さんが買っていただきたいなと思います。
排出量取引は、経済産業省の各資料にもあるように、GX二〇四〇ビジョンの方針に沿って進めるとされています。GX二〇四〇ビジョンでは、原子力発電の活用も取組に掲げています。原発回帰を促す目的がありますか。
○畠山政府参考人お答え申し上げます。二〇五〇年カーボンニュートラルを目指してGXを進めるといいますのは、これは排出削減を行いながら同時に経済成長も達成をしていく、こういうことで取り組んでいるわけでございます。これからその鍵となりますのは、CO2を出さない脱炭素電源をいかに確保していくか、こういうことでございまして、これまで電力の需要が過去二十年間ぐらい減り続けてきたわけですけれども、これが反転して増えていく中で、そういうCO2を出さない脱炭素電源を増やしていく必要がある、このように考えております。その意味では、CO2を出さない電気の代表でありますのは再生可能エネルギーと原子力発電でございまして、先般、閣議決定させていただきましたエネルギー基本計画の中でも、こうした脱炭素電源、これにつきましては最大限活用していこうということにしているところでございます。したがって、特にGXについて、原子力のためにやっているということではございませんけれども、脱炭素電源の重要な一つとして原子力発電も活用をしていく、こういうことで考えているところでございます。
○佐原委員 悪魔の言い訳というのがあるんですけれども、何でもかんでも、私の目から見ますと、経産省は原発推進の方に取り組んでいってしまうような気がいたしております。悪魔のささやきというんでしょうか。(原発を)クリーンエネルギーに位置づけるというのも、実は本当は無理があるのではないかなと思うんですよね。CO2は発電時は出さないけれども、そこに至るのには、このGX法案によって、いわゆる稼働の年数とか、その中には休んでいた期間はカウントしないとか、でも経年劣化ということもありますし、そういったことも含めて、これはやはり、GX法案と、あるいは、いわゆるデータセンターというのでお墨つきを得て、これからまたどんどん原発回帰に、したがって、いくのではないかなということを危惧しております。GX推進機構も含めGX政策そのものが、また経産大臣の采配で決められ、進められていく構造になっています。原発の長期稼働なども大臣次第と言えます。原発を更に推進し、原発をクリーンエネルギーにカウントしてしまうのは、日本政府が福島第一原発の事故後に取り組んだ政策との整合性がないのではないかなというふうに思います。一たび事故があれば、トランプ関税どころか、もっと大変なことになると思うんですね。私たちは、やはり今こそ小水力発電とか、あるいはペロブスカイトなどのようにジャパン・メイドの、そういった小国ならではの勝負で、それをまた海外に輸出するというような、そういった意味での取組が必要なのではないか。それが本当にGXにつながるのではないかなというふうに思うんです。この原発回帰だけは少し、少しというよりも大変私はがっかりしております。原発ということを繰り返していくことで、一体この国はどこに向かっていくんだろうなと思うんですよ。今、本当は、このGX法案を真に活用するためには、日本の産業力、技術力というもの、あるいは蓄電池も新しいのができました。省エネルギーの製品もたくさんできると思います。そういったことに支援をしていかなければ、また同じようなことが起きるのではないかなと思ってしまうんですね。ですから、日本という国が自然と共生をして生きてきた種類の人間であるということを考えたときに、本当は日本人に合わないんじゃないかなと思うんですね、そういう原発政策というのは。などといろいろ、いつも同じようなことを言って申し訳ないんですけれども、次回もこのことについてまた質問させていただきたいと思います。今日は本当に、お時間をいただきまして、お疲れのところ、本当にどうも、大臣、ありがとうございました。
YouTubeはこちら>>>
